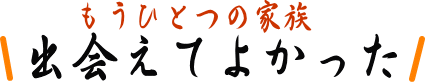ぼくはラッキーだった

会場からの質問
質問①
立ち入った話で失礼なんですが、Sさんご夫婦は、お互いどういうところに魅かれたのでしょうか。
Sさん
正義感ですね。
Aさん
たぶん私の母性が強かったんだと思います(笑)
司会
Sさんは、憎めないですよ。ごんたしていても憎めない。
里親さんのところに訪問看護に来ていた看護師さんが「里親さんがいつもSさんのことを口にしていたが、本人に出会って、こんなにすばらしい大人に育っているのを見て、自分も週末里親になりたい」とおっしゃったんです。
そんな広がりがありました。
里親の広がりは里親から、里親に関わった人から、知られていくのが良いと思いますね。
質問②
Sさんが、里親さんが亡くなられた時、非常に寂しい思いをしたという話をされました。
私は今育てている子どもが、親が亡くなった後も経済的に自立して生活していけるようにと考えてきました。
でも今日の話を聞いて、それよりも親の亡き後、里子や養子が寂しがらないようにするには、どうしたらよいかと…
こういうことがあれば悲しみが少なくなる、ということがあれば、教えていただきたいです。
Sさん
難しいなあ。でも、その時を迎える前から、そういう話題を出しておくことかな。
中学、高校時代から親子で覚悟をしておくことが必要ではないかなと思います。
「いつかは1人になるんやで」って伝えておくことが大事だと思います。
司会
この仕事の経験を通して思っていることですが、
1つは、自分の人生を思い返した時に、楽しかったなと思える思い出を作っておくこと。
喪失したものは戻ってこないけど、親と暮らした思い出は消えません。
もう1つは、子どもが親のことを一緒に語れる人をもつこと。
それが親子の絆を確認することにもなると思います。
「こうだったね、ああだったね」と話せる人をどれだけもつか、どれだけたくさん残してあげられるか、それが大切だと思います。
私たちの出会う子どもは、産みの親と育ての親との2度の喪失を経験するという特性をもっています。
それだけに、そんな存在が周りにいることは大切なことだと思います。

【2019年11月23日開催 第30回 里親制度をすすめるための講演】
「いろいろあってこそ、家族」
(はーもにい第135号より)