8年間の交流を通して築いた絆

里母からのお話
初詣に大喧嘩
今でもはっきり覚えている大喧嘩があります。
交流を始めた頃に、初詣で近くの神社に三人で歩いて行ったんです。
その時に彼が路側帯を仕切るブロックの上を歩くので
「危ないでしょう。歩道を歩きなさい」と注意しても、言うことを聞かないんです。
「死んだらどうするの。正月から」と怒ったら、余計にターと走っていったりするんです。
二人の息子を育てた経験から、反抗期の子どものすることだとは思っても、お預かりしている子どもだという特別な意識があって、ケガをさせてはいけないという思いもあるし…。
すると向こうもヒートアップしてきて「オレ帰る」と言ったんです。
一瞬エッと思ったけど、
「帰るんやったら、帰り。帰るってどこに帰るのよ」
「施設に帰る」
「一人で帰れると思ってんの」と大喧嘩になったんです。
今から思えば、大人げないと思いますが、私も真剣やったんです。その時、夫が「二人とも落ち着いて。今から初詣に行くんやから」「みんなが幸せになれるようにお祈りするねんから」と言いました。
後で「正月から何を怒ってんねやろ」と思ったけど、一方であの一件で親子になれたという思いもあります。言いたいことを言えば、相手も本音をぶつけてきます。
私たちを試していたとも思えるし、親子の関係に近づくには、こういうことも必要なことなのかも知れません。私にとって、一番の思い出です。
今は、彼がバイトとデートで忙しくて、ちょっと寂しい気がします。
もう一つは、洗濯です。季節や着る物によっては、家庭では毎日洗濯しないでしょう。ところが施設では毎日着替えていたので、「これ、明日も着て」と言うと、二日続けて同じ物を着ることには抵抗があったようです。
自分の家庭が全てではないので、押しつけるのは問題かなとも思いましたが、私の家のルールを貫きました。
里父からのお話
振り返って振り返って分かる「試し行動」
先ほど、うちに来た時に、どこかに行くかと誘っても、「別にない」という消極的な返事をしていたという話をしましたが、施設では行事や招待があってこれまでに、あちこち行っているんですね。
そんな時は幼児から高校生までの集団で引率者も若い職員という構成ですから、それを見る周囲の目が嫌だったようです。
でも、うちでは家族と見られますから、それが嬉しかったようです。だから、特別にどこかに行かなくても、買い物や食事に行くような、普通の暮らしでよかったということです。
妻が「試し行動」について話しましたが、初めての交流で、施設に帰る時になって突然「頭が痛い」と言い出したんです。
こちらは、風邪でも引かせたのかなと心配したんですが、後になって家庭養護促進協会のワーカーさんに話したら「帰りたくないので、頭痛のふりをしたのかな」と言われました。心境は複雑ですが、居心地のいい環境を作ってやりたいなと思いました。
最初の頃は、「どこまでやれば叱られるか」「どこまでなら大丈夫か」というような探りを入れてくることはありました。
《参加者からの質問》
質問①
子どもさんから、ご夫妻は何と呼ばれていたのですか?
里父
初日だけ本人が無理して「おやじ」と呼んだんです。ぎこちないので「無理してお父さんとか、お母さんと呼ばなくてもいいよ。自分の呼びたいようにすればいい」と伝えました。それ以後は「おっちゃん、おばちゃん」です。息子たちは「お兄ちゃん」です。
質問②
私の場合、自分の年齢からして「おばあちゃん」と言われそうに思うんですが、どうなんでしょうか?
里父
親子関係を求めてきているから、「お母さん」か「おばちゃん」になるかなと思いますが、あまり気にすることはないと思います。
里母
靴屋の店員さんから「お父さん、お母さん」と言われた時は、若く見られて私が嬉しかったぐらいのことで、その子を大切にする存在であれば、何であってもいいのかなと思います。
質問③
今、習字を教えているんです。小学生に「おばちゃん」というのもどうかなと思って「おばあちゃん」と言っているんですが、そんなに神経質にならなくてもいいですか?
司会
子どもが呼びたいように呼べばいいと思います。子どもは自分が感じているように呼ぶので、それを受け入れればいいのではないでしょうか。
質問④
実子と里子との感覚や感じ方の違いはありましたか?
里父
大きな差は感じなかったです。ただ、預かっているということで、ケガや病気については息子たちより気を遣いました。
【2019年11月11日開催 ボランティア里親の募集と説明会】
(はーもにい第131号より)
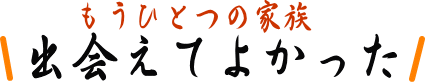


私も週末里親を希望しています。
この記事を読んで、子どもにとって何気ない日常がとっても新鮮で楽しいことなんだと伝わってきました。
いつか、わたしの所に子どもさんが来てくれるご縁ができたら、わたしもこんな風に一緒に過ごせたらと思いました。
いろんな方のお話を聞いたり読んだりして、子どもがどんなことに戸惑ったり、不安を感じたり、喜んだり、安心するのか知っておくことは私自身の安心や心構えになりました。
こうして体験を話してくださる先輩里親さんに感謝です。